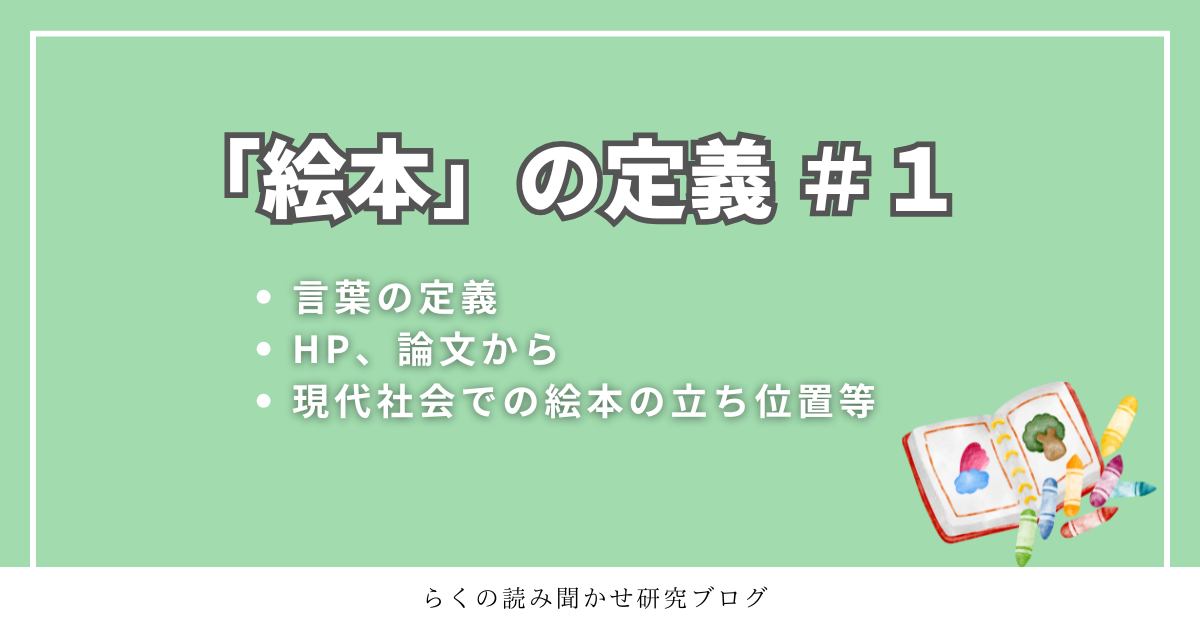さて、私の研究テーマとして「絵本の読み聞かせ」を取り上げるのであれば、何よりもまず、この研究における「絵本」と「読み聞かせ」についての定義から確認していくことにする。
この記事では、まず「絵本」の定義から始めることとする。
辞書や公式HPより考察
「絵本」とは言葉の通り、絵が載っている本である。文に沿った絵が描いてあり、言葉が平易でわかりやすく、誰でも読めるように漢字を多く使わないような簡単な文で書かれていれば、「絵本」であると認識することができるだろう。
ただ、「絵と文字があれば絵本である」、との定義だと、写真集や美術系の資料集と判別が難しくなる。また、近年は大人向けをうたい、漢字を使用したり長い文章を書く絵本も存在する。絵が存在せずとも、「絵本」と位置付けられるものもある。
「絵本」の定義の根底は、絵や文章だけではないようにも考えられる。
「絵本」というものについて、いくつか述べているサイトや本の引用を記載しておく。
デジタル大辞泉より
え‐ほん〔ヱ‐〕【絵本】
辞典・百科事典の検索サービス – Weblio辞書 国語辞典より検索https://www.weblio.jp/
読み方:えほん
1 絵を主にした子供向きの本。
2 江戸時代、絵を主にした通俗的な本。絵草紙。
3 絵をかくための手本。絵手本(えでほん)。
保育施設や出版社など現代で話される「絵本」は、主に1のことを指す。
ポイントとしては、「絵を主にする」という部分である。
小説やエッセイ、児童書でも、絵が含まれていることはもちろんあるが、それはいわゆる「挿絵」文章を補助するような役割で、絵は主となる要素ではないと言える。あくまでそれらは、文章が主となる要素だ。
絵本ナビより
現在登録者2000万人であるサイト「絵本ナビ」にて、このように記載されている。
絵本というのは、絵と文章があり、両方があって初めて完成するものです。表紙があり、ページをめくることで物語が進んでいき、最後の裏表紙まできて「おしまい」となります。字の読めない子ども達は、文章を大人に読んでもらい、絵の中からさまざまな事を読み取っていきます。ページをめくりながら、自分のペースで物語を進めていくことができます。だからこそ、絵本というのは「赤ちゃんから大人まで、どの年齢の人たちでも楽しめる」のだと言えます。
絵本ナビ絵本の魅力ってなに? どうして絵本を読むの?(閲覧日:2025/09/29)
https://www.ehonnavi.net/about/picturebooks.asp?srsltid=AfmBOoqPN75jhQHK9s7CqbAox4wzY4vI1nInjyMVS-8ouM7gRg63zphm
絵本は内容だけでなく、表紙と裏表紙まで含めてひとつの物語になっているものが多い。始まりで表紙を見せ、内容が終わり、裏表紙になって「おしまい」を伝えるまで、一つの物語なのだ。子どもに絵本を見せる立場の者は、このことを十分理解しておく必要がある。
公益社団法人 全国学校図書館協議会より
次は、公益社団法人全国学校図書館協議会より、「全国学校図書館協議会絵本選定基準」から、絵本の基準を見てみる。
この公益社団法人は、学校図書館の充実と青少年読書の推進活動を目指して、研修やコンクールなどの活動を行う団体である。
基本原則
絵本とは、書籍の形態をもって、絵または絵と文の融合から生まれる芸術であると考える。
公益社団法人全国学校図書館協議会公式HPから、全国学校図書館協議会絵本選定基準(閲覧日:2025/10/02)
- 原則として、絵の比重が形式的にも、内容的にもその本の半分以上を占めていること。
- 画集、単純な写真集、図鑑、低俗なマンガ本・劇画等は対象としない。
- 絵本は主として、乳幼児・児童を対象としたものであるが、青少年、成人向きのものも考慮する。
- 絵雑誌は対象としない。
こちらでもやはり、「絵の比重が大きい」という内容の記載がある。絵本にとっては、「絵」の占める割合が大きいことがわかる。
他に絵が載っている、画集や写真集等とは区別しているものとする。
論文より
また、筆者が愛読している近藤先生・辻本先生の論文には、このように記載されている。
絵本とは、文と絵から成り立つ世界、文と絵が響きあって作り出しているトータル的な芸術的世界である。
近藤 文里・辻元 千佳子,2006「絵本の読み聞かせに関する基礎研究とADHD児教育への応用(1)ー教育の展望と本研究の課題ー」滋賀大学教育学部紀要,教育科学No.58,65-77
絵本は一冊で物語が完結し、その中で一つの世界を形成しているというのが、大事なポイントである。
絵と文、どちらもの質が重要である。
以上の定義より一旦考察してみる
以上の内容から考えると、まず絵本は、かかれている絵と文を合わせて一つの物語を作る芸術作品の一つである。絵本の物語は、ページの最初から終わりまで連続していき、ページをめくると物語が進む。
当たり前のように感じるが、児童書や小説、漫画などは、一冊だけでは完結しないものも多い。
また、写真集や作品集などは、基本的に一ページに一作品で完結している。前後ページの作品に連続性はないし、文章も、そのページに書かれている作品についての詳細であったり、一つの物語にはなっていない。
だが、絵本は最初から最後のページまで、絵も文もつながって一つの物語、いわば世界を形成している。そのため、絵と文章の流れが、正しく整合性がとれている作品でないと、よい絵本とは言えないだろう。
現実場面での絵本の立ち位置
幼児が通う保育施設、幼稚園等では、絵本は欠かせない存在である。幼児にとって大切な遊び道具であったり、また絵本の読み聞かせは、保育者にとっても子どもにとっても、重要な位置づけにある。
園で実際に働いている方々の話によると、活動と活動と合間の切り替え時や、活動前に内容に関連する絵本を読んでイメージを高めるなど、子どもの集中や気持ちの切り替えに使うような印象があるという。
保育施設や図書館等だけでなく、家での場面にも絵本はよく活用されている。家族に読んでもらったり、親が忙しいときは一人で読んだり、プレゼントとして送ってもらったり、家庭の場面でも絵本の役割は大きくなっている。
親はわが子のためにと、図書館でまとめてたくさん重い本を借りたり、仕事終わりで眠い目をこすりながら、就寝時の子どものために読んだりしているという。まさにこれは愛だ。莫大な愛である。
また、2020年以降より日本には「絵本ブーム」が来ているといわれている。
絵本の対象は幼児や児童であるが、大人向けの絵本の販売もあり、出版業界にも大きな波が来ており、市場が拡大しているという。
→東洋経済ONLINE(2023/06/09記事)少子化なのに「絵本」市場は拡大の知られざる側https://toyokeizai.net/articles/-/674644
絵本は、現代社会に様々な形で浸透していると言えるだろう。