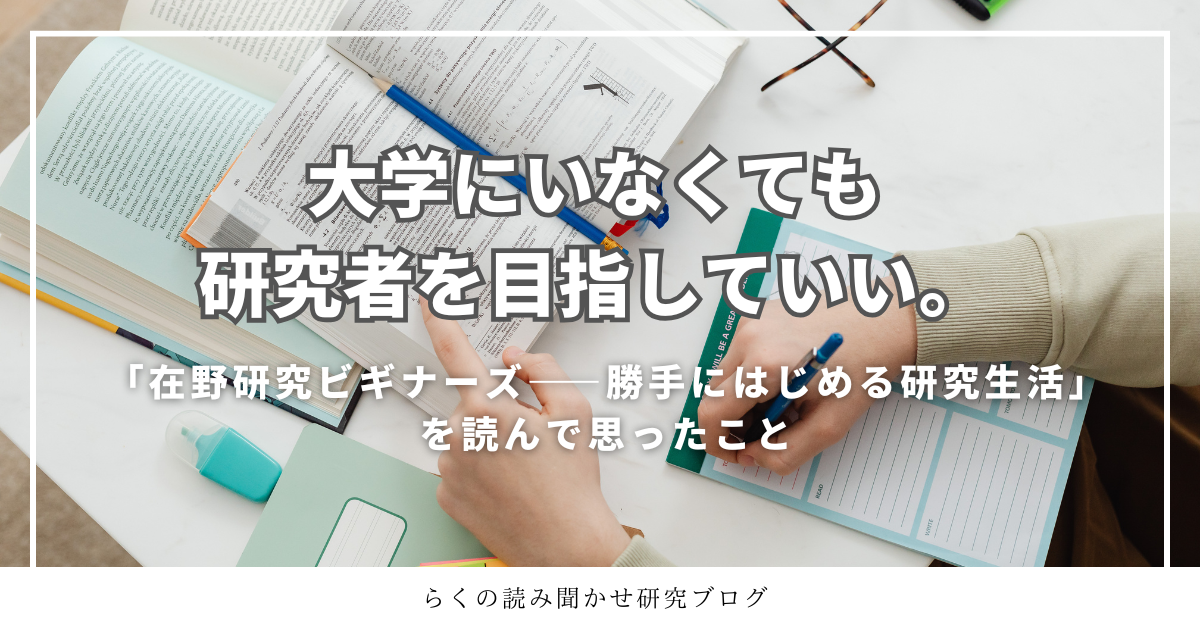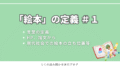「在野研究」という言葉を聞いて、まだ私は日が浅い。しかし、調べずにはいられないと思った。「やっぱり読み聞かせ研究がしたい」と家族に話したところ、こういう人もいるよ、と教えてもらった言葉だった。
在野研究とは、ごく簡単に、大学に所属を持たない学問研究のことを指している。
「在野研究ビギナーズ――勝手にはじめる研究生活 」(編者・荒木優太)序 あさっての方へ
まさに今の私にぴったりかもしれない。
そう思えた。
この本「在野研究ビギナーズ――勝手にはじめる研究生活 」は、現役の在野研究者15人の、体験や研究方法などを、本人の語りで集めたものである。専攻の学問について、政治学、哲学、生物学、文学研究など様々。
語り口も様々で、研究方法や実践例をしっかり記載している章もあれば、ただひたすら研究を初めて今に至るまでの流れをガンガン書いている章もあり、非常に読みごたえがあってよい本であった。
また15人とも研究者として目指しているものも違っていた。ただひたすら勉強が好きだという人もいれば、所属がなくともアカデミックな質を求めて論文投稿をしている人、論文はそこまで書いていない人など、文字通り多種多様な研究者の様子が見えた。
この本を読んで、自分が「研究をしたい」と思った動機を、書かずにはいられなかった。
研究者を目指したくなった私の経験
大学三年生からコロナ禍に突入し、将来の不安から、とりあえず社会人になってしまった。
自分自身が頭でっかちなのと、所属の専攻の質として「大学院に行く=資格を取るため」という概念が定着していたこともあり、周囲に「研究が好き」「勉強が好き」だと言い出せずにいた。
実際、同じ専攻だけでなく他の学部も、大学院に行く人は、就活時に研究室の実績や推薦を得たいとか、お金にそこまで困ってなくて、学生をまだ続けたいから、と公言している人もいた。(実際にそれで院に通う人に何人も会った)
性別もあるのだと思う。割と大学の友人関係やサークルでは、「夜だと男子が女子を送る」とか「部内でも男子と女子で分ける」「飲み会に来るのは男だけ」「女子はいつか結婚するからキャリアはそこまで心配しない」みたいな、性差を感じるタイミングはものすごく多かったように思う。
私自身も正直なところ、入学までは院に進学し、資格を取得して就職するつもりであった。
高校生当時は「大学」「大学院」というものがどういう場所か分かっておらず、
「そこに入って卒業すれば将来安泰だろう」
などという幻想を抱いていた。
入学して気づいたのは、臨床場面での学びの面白さは感じていたが、純粋に心理学という学問の変遷についてや、過去行われた様々な実験、研究などに興味を強く感じていた。もともと座学は全く苦痛ではなく、皆が眠い目をこすっていたり、手元にスマートフォンを隠している中で、教授の話が大変面白く感じていた。事例検討なんかはものすごく楽しかったが、いくら自分がやる気を出しても、グループの総意にならないとどうしようもなかった。
「とりあえずだらっと受けて、授業が終わったら友達と愚痴る」という人が大半であったので、自分の考えは話すことができなかった。学部の友人らと、もっとこう、ヒステリー症状が解明されたときの中世ヨーロッパの状況についてだとか(妙に油絵が情熱的で神秘的に見えた)教授が話したカウンセリングの興味深い事例についてだとかを、友人らと討論してみたかったな、と思った。
卒論を書く最後の年、初めて論文というものに触れ、まずは圧倒的な面白さに惹かれた。本より高価でなく、アクセスが容易で、すぐ目を通すことができる、質の高い研究や豊富なテーマに心を奪われた。分厚く翻訳が難しい専門書よりも、読むのが楽しかった。
自分が研究したいテーマについて、様々な論文が投稿されているのがわかり、自分の世界の狭さを痛感した。それとともに、私自身が感じていた感情や経験が、だんだんと言語化されていく感覚に、心が躍った。
「正直資格とかより研究したい」
卒論を書き上げたとき、そう思った。
卒業論文では、本来未就学児を対象に読み聞かせを行いたかったが、コロナ禍の影響で受け入れてくれる施設がなかったことがあり、在校の大学生を対象に行った。それが私に大きな後悔を残していた。
本を実際に読んで頷かずにはいられなかった
自分語りが長くなってしまったが、今からは実際に本の内容に触れてみたい。
どの人も、強い熱意と、生活の中で自分で時間を作りながら研究を続ける工夫が感じられた。
私が感じていたように、やはり大学を卒業してから、文献や資料のアクセスが課題と感じる、と記載していた方が多かった。
もちろんインターネットの普及で数十年前より格段にやりやすいとは思うが、それでも大学というのはすごい。特に論文の取り寄せについては、公立図書館よりも大学図書館の方が上で、かつ大学に所属していないとリファレンスサービスなど活用できない場所が多い。
私も社会人になってから、ciniiにPDFを掲載していない論文を取り寄せようと思い、再度卒業した大学図書館に一般利用登録をしたのだが、論文の複写は学生、教授しか受け付けていないといわれた(悲しい)
個人的に特に好きだったのが、第五章「点をつなごうとする話」の内田明さんの話である。徹頭徹尾、素晴らしく熱量と愛を感じて圧倒された。この方は日本語活字というテーマにハマっており、印刷や活版だけでなく、インターネット上のフォントなどの開発も行っているそうだ。私自身がフォントに造詣はないが、この熱に圧倒させられた。
私もこれぐらいになりたいと思ったうちの一人だった。
その他参考になった部分を書いてみる。
- 制限はありつつ、図書館サービス等活用しまくるとよい。国立図書館登録もおすすめ
- アカデミックな質の担保のため、学会への投稿を目標にするとよい
- 学会や雑誌投稿だけでなく、ネットにPDFを発表・ブログやSNSで研究者とつながるのもおすすめである(一人で研究をすると煮詰まりやすいので)
- 研究者だけでなく読書会やセミナー、勉強会も顔を出す
- 在野研究者が学会に所属する際、肩書を聞かれることがある(肩書なしでOKな学会もあればかならず所属先を書かねばならない学会もある。職場を書く際は上司の許可を取る)
学び続けたいという気持ちを持ち続けたい
当たり前かもしれないが、どんな形でも、どんな状況でも、「やりたいことはやっていい」のだと、時間が経って気づくことができた。
身の回りには、今でも「研究したい」「勉強したい」と話す人がいないため、なかなか口に出すことは困難であったが、この本を読んで、
「あぁ、好きだと言っていいのだな」
と安堵することができた。
特に社会人になると、対外的にわかりやすさが求められているように思う。
仕事で専門的にやっているとか、資格を持っているとか、学会に所属しているとか、である。
だが結局のところ、大切なところは、「いかに自分が熱量をもって研究・学びに取り組めるか」であって、その質やレベルの高さは、他者がどうこう言える部分ではない。
そして何よりも、「学び続けられる」人が、真の研究者になるのだろうと考える。
私も社会人になってしまい、研究以外のスケジュールも多い。研究が仕事の人よりもなかなか時間をとることが難しいときもある。生活のための資金も稼がねばならない。持病の薬をもらいに行く必要もあるし、家族の予定もある。
そんな中で研究を志そうと思ったとき、この本が、一つの指針になったように感じた。
在野研究には明日がない。明日は、労働や育児や家事や病院通いといったもろもろのスケジュールで埋め尽くされているから。(中略)
「在野研究ビギナーズ――勝手にはじめる研究生活 」(編者・荒木優太)序 あさっての方へ
それでも、「あさって」ならばある、「あさって」こそある、と信じている。
あさってこそ、あさってこそと、自分を鼓舞して、前に進みたいと思う。