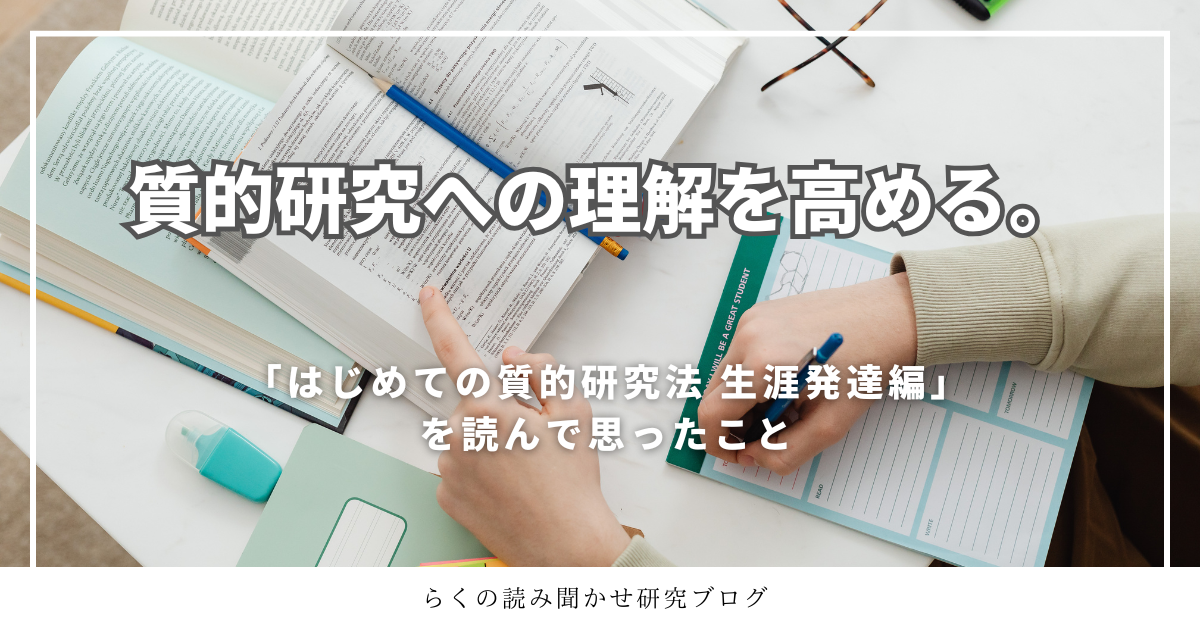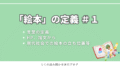学部時代の学びの中では、質的研究よりも量的研究、数値の分析の方を重点的に学んだ。そのため、質的研究に関する知見が薄いと思い、参考になる文献をいくつか読んでいるが、よい本があったので紹介したい。
「はじめての質的研究法 生涯発達編」(編集:遠藤 利彦・坂上 裕子)
この本は、まず質的研究についての概論、解説からはじまり、複数の研究者の質的研究について、実践内容をベースに記載している。質的研究、だけだとざっくりしているが、インタビュー等の面接(半構造化面接がほとんど)と、観察法である。面接は大人、観察法は幼児、親子が対象である。
分析の結果だけでなく、分析方法についてかなり記載しているので、これから質的研究をしたい、心理学をベースに研究したい人は必ず参考になるだろう。
ページ数は多いが、一つ一つ実際の研究内容をもとに記載しているので、わかりやすく読むことができた。執筆者の研究であったり、中には研究室の質の良い修士さんの論文を上げている方もいらっしゃり、最後まで楽しく拝読できた。
用語についても、大学の時ちらっと触れたり、論文で読んだことあるものの知識の確認ができた
(横断的研究、縦断的研究の違い・研究者倫理・研究対象者へのフィードバックや配慮など細かい部分も確認できる)
私は卒業論文では質問紙を取って、読み聞かせ後の前と後の尺度の差をt検定で求めた。そのため、質的研究にはあまり触れてこなかったように思う。授業でも、方法などの名前はちらっと聞くけど、なぜそれを採用するのか、どういう点で違うのかなどはわかっておらず、漠然とした知識しかなかった。
読み聞かせ関連の研究となると、先行研究でも聞き手の幼児の観察であったり、読み聞かせ場面の録画や音声の分析等になる。未就学児だと必然的に文字が読めなかったり、発話も大人ほど流暢ではないので、質問紙や長時間の面接が難しい可能性が高い(当たり前だが)
そのため、質的研究に関する知見が必要になると思ったのだ。
特に観察時の記録の取り方「フィールドノート」については、かなりイメージすることができた。フィールドノートについては、もしやるとするなら、相当な訓練が必要になりそうな模様だ。
(メモの取り方、記載、いかに自分が周囲の環境に影響を与えないかなど、観察時は考えなければならないことが多すぎる、世の中の研究者すごい、絶対すぐに思い立ってできるものではない、当たり前だけれど)
この冊子は全部で4冊あり、様々な内容で本が分けられている。私は未就学児を対象にすることが多いため、「生涯発達編」を一番目に読んだが、他の編もぜひ読んでみたいと思った。